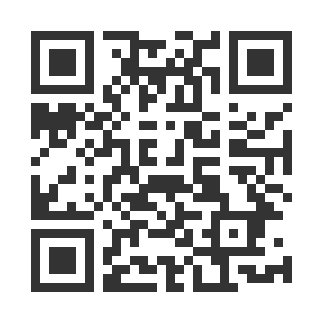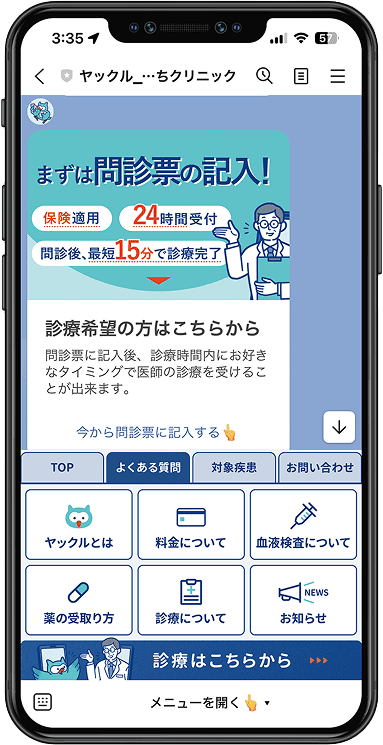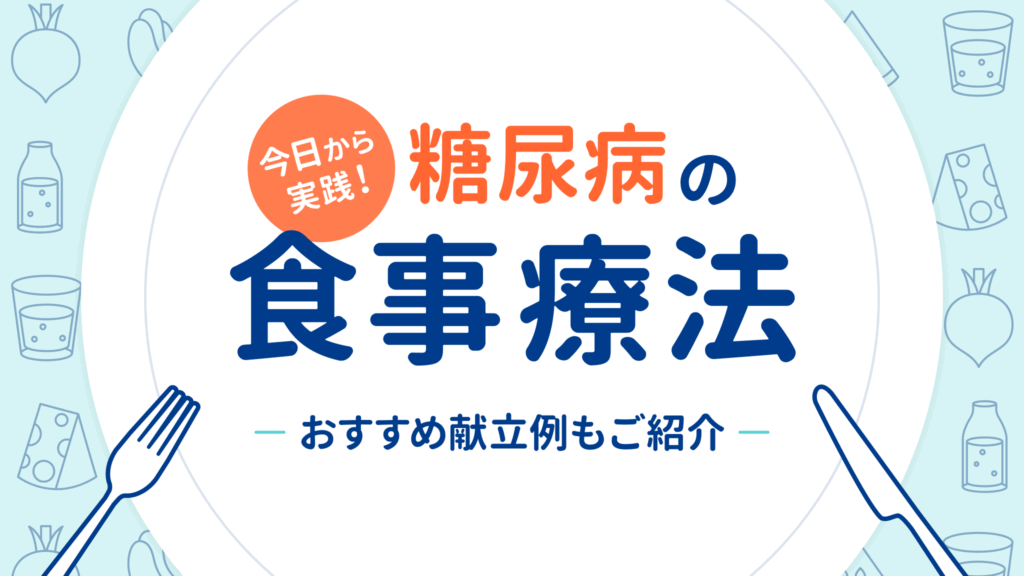
「血糖値が高めと言われたけど、何を食べたらいいのかわからない」「糖尿病の家族に、どんな食事を作ればいいのか悩んでいる」
そんな不安を感じていませんか?
糖尿病は、食事の工夫によって血糖値を安定させることができる病気です。特に2型糖尿病では、食生活の見直しが治療の第一歩となります。
この記事では、糖尿病の方が日々の食事で気をつけたいポイントをわかりやすく解説するとともに、すぐに取り入れられるおすすめレシピをご紹介します。
血糖値をコントロールしながら、無理なくおいしく続けられる食事のコツを知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
なぜ糖尿病治療に「食事療法」が重要なのか?
糖尿病の治療は、「食事療法・運動療法・薬物療法」の三本柱によって成り立っています。なかでも食事療法は、血糖コントロールの基盤となる最も重要な治療手段と位置づけられています。
過剰に糖質を摂ると血糖が急激にあがる「血糖値スパイク」に注意
白米やパン、菓子類、甘い飲み物などの糖質を一度に多く摂取すると、血液中の血糖値が急上昇します。この現象は「血糖値スパイク」と呼ばれ、身体に様々な悪影響を及ぼします。
血糖値が急上昇すると、それを正常値に戻すために、膵臓はインスリンを大量に分泌して対応します。この過剰な負担が繰り返されることで、膵臓が疲れてしまい徐々にインスリンをうまく分泌できなくなります。
また、血糖値が高い状態が恒常的に続く場合にも、膵臓は休む間もなく働き続けることを余儀なくされ、結果的に同様の機能低下を引き起こします。
膵臓の機能が低下すると、血糖値を適切に下げることが難しくなり、最終的に血糖値が慢性的に高い状態となる「糖尿病」の進行リスクが高まります。
間食や加糖飲料の習慣による「恒常的な高血糖」
さらに、間食を頻繁に摂取したり、甘い飲み物を常に摂取する習慣がある場合も注意が必要です。
このような生活習慣により、血糖値が慢性的に高い状態が持続し、次のような悪影響を及ぼします。
- 膵臓が休むことなくインスリン分泌を続けなければならない
- 酸化ストレスや慢性炎症を引き起こしやすくなる
これらの要因が重なることで、膵臓の疲弊と機能低下が進行し、糖尿病の悪化を助長することになります。
食事管理が糖尿病治療の要となる理由
糖尿病の進行は、
- 急激な血糖値の上昇(血糖値スパイク)
- 恒常的な高血糖状態
によって、膵臓に持続的な負担がかかることから始まります。
したがって、日々の食事内容や食べ方を工夫し、血糖値の急上昇を防ぎ、膵臓を保護することが、糖尿病治療における最も基本的かつ重要な戦略となります。
適切な食事管理により血糖コントロールが安定し、さらに合併症の予防や生活の質(QOL: Quality of Life)の向上にもつながることが期待できます。
糖尿病食事療法の基本|血糖コントロールのために押さえたい5つのポイント

糖尿病の食事療法においては、「○○を絶対に食べてはいけない」といった厳しい制限を設けるのではなく、血糖値の急激な上昇を防ぎ、膵臓への負担を軽減するための食習慣を整えることが重視されます。
ここでは、血糖コントロールを安定させるために押さえておきたい、基本的なポイントをご紹介します。
1. まずは野菜から食べるベジファーストがおすすめ
食事を始める際は、まず野菜や海藻類、きのこ類などの食物繊維を多く含む食品から食べることが推奨されます。
食物繊維には、糖質の吸収を緩やかにする働きがあり、結果として食後血糖値の急上昇(血糖値スパイク)を抑える効果が期待できます。
特に、葉物野菜やきのこ、海藻類は、低カロリーかつ食物繊維が豊富なため、積極的に取り入れるとよいでしょう。
2. 主食は「量と質」に注意する
血糖コントロールのためには、主食の摂り方にも工夫が必要です。
白米やうどん、食パンなど精製された炭水化物は、血糖値を急激に上げやすいため、以下のような工夫が推奨されます。
- 麦ごはんや雑穀米を取り入れる
- 白米の量を控えめにし、適量を心がける
「完全にごはんを抜く」という必要はありませんが、主食の質を見直し、摂取量を適切に管理することが重要です。
3. 低カロリー・高食物繊維の食材を活用する
血糖コントロールを意識しながら食事の満足感を高めるためには、こんにゃく、きのこ類、海藻類、葉物野菜といった低カロリーかつ食物繊維が豊富な食材を積極的に取り入れることが有効です。
これらの食材は、「かさ増し」としても優れており、適量のエネルギー摂取を維持しつつ、満腹感を得やすくなります。
4. 良質なタンパク質をバランスよく取り入れる
筋肉量の維持は、血糖コントロールにおいて重要な役割を果たします。筋肉はブドウ糖をエネルギー源として利用するため、筋肉量が減少すると血糖値が上がりやすくなる傾向があります。
そのため、食事には良質なタンパク質源(脂肪の少ない肉、魚、卵、大豆製品など)を適度に取り入れることが推奨されます。
なお、腎症を合併している場合は、タンパク質摂取量に注意が必要です。その場合は、医師や管理栄養士の指導のもと、脂質からエネルギーを補うなど、個別に対応することが望まれます。
5. 間食やジュースは控えめに
間食やジュースは、血糖値を常に高い状態に保ちやすく、膵臓への負担を増大させる要因となります。基本的には、間食を控え、加糖飲料の摂取を避けることが推奨されます。
間食が必要な場合でも、
- 無糖ヨーグルト
- 素焼きナッツ
- 茹でた野菜
など、血糖値に影響を与えにくい食品を選びましょう。
糖尿病食事療法を続けるために大切なこと
糖尿病食事療法においては、特定の食品を完全に制限することよりも、血糖値の急上昇を防ぐための食べ方・選び方を身につけ、日々の生活に無理なく取り入れることが最も重要です。
小さな習慣の積み重ねが、血糖コントロールの安定につながり、糖尿病の進行予防や合併症リスクの低減にも寄与します。
生活に取り入れるための工夫|続けられる食事療法のコツ

糖尿病の食事療法は、理論を理解するだけでなく、日々の生活のなかで無理なく続ける工夫を取り入れることが成功の鍵となります。
ここでは、生活シーンごとに実践できる具体的な工夫をご紹介します。
【朝食時の工夫】忙しい朝でも食事リズムを崩さない
血糖コントロールを安定させるためには、朝食を欠かさず摂ることが重要です。忙しい朝でも、できるだけ以下の工夫を取り入れましょう。
- 野菜や無糖ヨーグルトなど、食物繊維を含むものから先に摂取する
- 時間がない場合は、無添加の野菜ジュースや蒸し野菜を活用する
- パンや白米のみといった糖質偏重の食事は避ける
朝食でも「ベジファースト」を無理なく取り入れることが、血糖値管理に役立ちます。
【昼食・外食時の工夫】血糖コントロールを意識した選び方をする
外食やコンビニ利用が必要な場合でも、選び方を工夫すれば血糖コントロールをサポートできます。
- 主食の量は少なめを選択(小盛り、半ライスなど)
- 野菜がしっかり摂れる定食スタイルを選ぶ
- ドレッシングやソースは自分で調整できるように別でもらうようにする
- 揚げ物よりも、焼き物や蒸し物、煮物を優先する
完全に外食を制限する必要はありません。できる範囲で選択を工夫することが、長く続けるためのコツです。
【間食時の工夫】安心できる常備食品を準備しておく
小腹が空いたときに甘い菓子類に手を伸ばさないためには、あらかじめ低糖質・低カロリーの食品を常備しておくことが有効です。
おすすめの常備食品
- 無糖ヨーグルト
- 素焼きナッツ(食塩・油不使用)
- 茹でたブロッコリーやきゅうり
- 無糖の寒天ゼリー
間食は少量ずつ、血糖値に配慮したものを選ぶようにしましょう。
【飲み物選びの工夫】無糖・ノンカロリーを基本にする
飲み物からの糖質摂取を防ぐためには、常に無糖・ノンカロリーの飲料を選択肢として用意しておくことが重要です。
- 自宅や職場に水・緑茶・麦茶・ウーロン茶を常備
- 外出時にも無糖のペットボトル飲料を持参
- 「選ぶ手間」を減らし、自然に無糖飲料を選べる環境をつくる
選択のハードルを下げ、自然と健康的な飲み物を選べる環境を整えましょう。
【食事準備の工夫】負担を減らして無理なく続ける
忙しい日々の中で食事療法を続けるためには、事前準備を習慣化することが有効です。
- 麦ごはんや雑穀ごはんをまとめて炊き、小分け冷凍
- ほうれん草のおひたし、きのこソテー、ひじき煮など副菜の作り置き
- 低糖質のおかずや間食を常備しておく
「選ぶだけ・温めるだけ」でバランスの良い食事が整う環境を作ることが、無理なく続けるためのポイントです。
おすすめレシピ|無理なく続けられるヘルシーメニュー・糖質控えめメニュー

糖尿病の食事療法では、無理に制限するのではなく、血糖値への影響を抑えながら、栄養バランスを整えた食事を楽しむことが大切です。
ここでは、日々の食事に取り入れやすい、ヘルシーメニューと糖質控えめメニューをそれぞれご紹介します。
ヘルシーメニュー:鶏むね肉と野菜の蒸し煮
こんな症状の方におすすめ
- 糖尿病が初期段階の方(食事改善で血糖値を安定させたい方)
- 脂質摂取量をコントロールしたい方(脂質異常症が心配な方にも)
- 高血圧など合併症予防を意識している方
材料(2人分)
- 鶏むね肉(皮なし)…200g
- キャベツ…1/4個
- しめじ…1/2パック
- にんじん…1/2本
- 塩…少々
- こしょう…少々
- 酒…大さじ1
※アルコール分は加熱で飛びますが、より厳密に糖質制限を意識する場合は、酒を水に置き換えても構いません。
作り方
- 鶏むね肉は一口大にそぎ切りにし、塩・こしょうを軽くふる。
- キャベツはざく切り、しめじは石づきを取り小房に分け、にんじんは薄切りにする。
- フライパンに野菜を敷き、その上に鶏肉をのせ、酒を回しかける。
- ふたをして中火で蒸し煮にし、火が通ったら完成。
ポイント
- 油を使わず蒸し煮にすることでカロリーを抑えられます。
- 野菜の水分を活かして調理するため、塩分を控えめにしても美味しく仕上がります。
糖質控えめメニュー:豆腐ときのこの和風あんかけ
こんな症状の方におすすめ
- 糖尿病が進行してきた方(糖質管理をより重視したい方)
- 腎機能が低下し始めた方(たんぱく質量を調整しながら栄養を確保したい方)
材料(2人分)
- 木綿豆腐…1丁(約300g)
- えのきだけ…1/2パック
- しいたけ…4枚
- 小松菜…1/2束
- だし汁…150ml
- しょうゆ…小さじ2
- 水溶き片栗粉(片栗粉小さじ1+水小さじ2)
- みりん…小さじ2
※みりんを使用する場合は量を控えめにし、気になる方は「みりん風調味料(低糖タイプ)」を代用してください。
作り方
- 豆腐は軽く水切りし、食べやすい大きさに切る。
- えのきは根元を落として半分に切り、しいたけは薄切りにする。
- 小松菜はざく切りにする。
- 鍋にだし汁を温め、きのこと小松菜を加えてさっと煮る。
- 豆腐を加え、しょうゆ・みりんで味を調える。
- 最後に水溶き片栗粉でとろみをつける。
ポイント
- あんかけにすることで、少量の調味料でもしっかり満足感が出ます。
- ごはんにかけず、単品で楽しむことで糖質摂取量を抑えられます。
血糖値が気になる方の食事Q&A
Q1.食事療法だけで血糖値を正常に戻すことはできますか?
A1. 2型糖尿病の初期段階では、適切な食事療法と運動療法だけで血糖コントロールが改善し、薬物療法を回避できる場合もあります。ただし、血糖値の状態や合併症リスクによっては、医師の判断で薬物療法が必要となることもあります。自己判断せず、必ず医師や管理栄養士の指導を受けながら進めましょう。
Q2.野菜をたくさん食べれば、他の食事は気にしなくてもよいですか?
A2. 野菜は血糖コントロールに役立ちますが、それだけで十分とは言えません。炭水化物・タンパク質・脂質のバランスをとり、適切なエネルギー摂取量を守ることが必要です。食事全体のバランスを整えたうえで、野菜を積極的に摂ることが理想です。
Q3.フルーツは血糖値に悪いのでしょうか?
A3. フルーツにも果糖が含まれるため、過剰摂取は血糖値を上昇させる原因となります。ただし、適量であればビタミンや食物繊維の供給源として役立ちます。目安としては1日1〜2種類、食後に少量(例:みかん1個、いちご5粒程度)を意識しましょう。
Q4. 外食が続いてしまったとき、どのようにリカバリーすればよいですか?
A4.外食が続いたあとは、次の日からバランスの良い食事に戻すことが大切です。
- 野菜中心の食事にする
- 主食量を控えめにする
- 油脂や塩分を控える
といった工夫で、血糖コントロールをリセットしていきましょう。一度の外食で過剰に落ち込まず、長期的に整えていくことが重要です。
まとめ:糖尿病と上手に付き合い、毎日の食事から健康を守ろう
糖尿病は初期には自覚症状が少ないまま進行するため、早期からの血糖コントロールが重要です。
中でも、無理なく生活に取り入れられる食習慣の工夫は、血糖値の安定化や合併症予防、健康寿命の延伸に役立ちます。
しかし、体質や病状に合わせたエネルギー量や栄養バランスの調整を、一人で続けるのは容易ではありません。適切な食事療法を行うためには、医師や管理栄養士による専門的なサポートが欠かせません。
「この食事内容で本当に合っているのだろうか」
「血糖値がなかなか安定しない」
そんな不安を感じたときは、迷わず専門家に相談しましょう。
近くに相談できる医療機関がない場合でも、オンライン診療サービス『ヤックル』を活用すれば、自宅にいながら医師に相談し、食事療法や血糖コントロールのアドバイスを受けることが可能です。
正しい知識と、続けられる環境を整えながら、未来の健康を守っていきましょう。
今すぐLINEで簡単に診療を始めませんか?




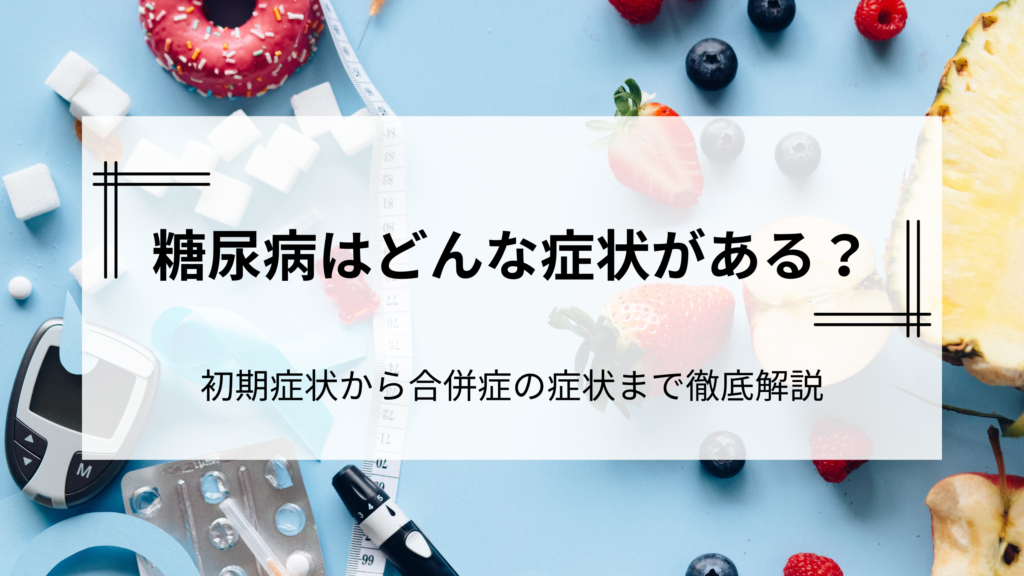
のコピー-1024x576.png)